電子帳簿保存法とは?2023年12月末までにやっておくべきこと
2024/07/23 働き方改革2022年1月に改正された電子帳簿保存法。実は、2023年12月末まで宥恕措置が取られています。2023年12月末までに企業はどのような対応をしておくべきなのでしょうか。
この記事では、改正された電子帳簿保存法と2023年12月末まで対応すべきことについて解説します。
電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、企業や個人事業主などが電子的な形式で帳簿を作成・保存する際に遵守しなければならない法律のことです。この法律は、電子帳簿を保存することにより、企業や個人が財務管理をより効率的に行い、財務記録の正確性と信頼性を高めることを目的としています。
電子保存の形式
電子保存の形式は3つあります。まずは、電子保存の形式から見ていきましょう。
電子帳簿等保存
言葉の通り、電子で作成した帳簿や書類を電子データのまま保存することです。会計システムで作成した総勘定元帳や、損益計算書、仕訳帳などが該当します。
スキャナ保存
紙の書類をスマホまたはスキャナなどで読み取り、電子データとして保存することです。請求書や領収書、取引関係の書類の控えなどが対象です。スキャナ保存として認められている機器は、スキャナ・デジタルカメラ・スマホなど。解像度は200dpi以上と決められています。
電子取引データ保存
電子データでやり取りした取引情報を電子のまま保存することです。自社で発行した書類や取引先から発行された書類が該当します。
インボイス制度・電子帳簿保存法のおさらい&おすすめツールはこちらから【HYPER VOiCE】インボイス制度・電子帳簿保存法ポータル
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正内容

電子帳簿保存法は、2022年1月に改正案が施行されています。次に、改正された電子帳簿保存法の内容を見ていきましょう。
電子帳簿保存法承認制度の廃止
今までの電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存やスキャナ保存を希望する場合、事前に税務署長の承認が必要でした。
2022年1月以降は、この承認手続きが不要となっています。承認が不要になったことで、事務手続きの負担が減り、電子帳簿保存を導入しやすくなりました。
タイムスタンプの付与要件が一部緩和
スキャナ保存・電子取引によるタイムスタンプ付与期間が延長されています。これまでは、受領者が紙の書類(領収書など)をスキャンする場合、署名を行い3営業以内にタイムスタンプを付与する必要がありました。改正後は、期間が延長し最大で2カ月までの付与が可能となっています。
スキャナ保存の要件が緩和
スキャナ保存をする際、訂正・削除履歴が残るシステムを利用する場合は、タイムスタンプの付与が不要になりました。
検索要件の緩和
今までは、範囲指定や項目の掛け合わせなど複雑な検索機能を必要としていました。改正後は、取引年月日や取引金額、取引先になるなど緩和されています。
電子取引データの電子化対応の義務化
電子取引データ保存への電子保存対応が義務化されました。電子取引でのやり取りについては、電子保存が必須、紙での保存は廃止ということになります。電子化が義務化されたため、国税申告を行う際、紙の書類では受領されなくなります。
インボイス制度・電子帳簿保存法のおさらい&おすすめツールはこちらから【HYPER VOiCE】インボイス制度・電子帳簿保存法ポータル
対象の企業と罰則について
では、この改正された電子帳簿保存法はどのような企業が対象なのでしょうか。また、厳守しなかった場合、罰則はあるのでしょうか。ここでは、電子帳簿保存法の対象の企業と罰則について解説します。
改正された電子帳簿保存法の対象の企業
電子帳簿保存法は、所得税や法人税の国税関係の帳簿書類の保存義務者が対象です。法人税を納めている普通法人や公益法人、所得税の納税義務がある個人事業主が当てはまります。基本的に、ほとんどの企業が対象となるでしょう。改正された電子帳簿保存法についても、同様の企業が対象となります。
違反した際の罰則はある?
違反した場合は以下のような罰則を受ける可能性があります。
青色申告承認の取り消し
正しく国税関係の帳簿書類を保存されていない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告が取り消されてしまうと、最大65万円の特別控除が受けられなくなったり、会社の信用が損なわれたりします。
追徴課税・推計課税
保存したデータに、改ざんや隠蔽が見つかった場合は、通常の追徴課税である35%にプラスして、10%の重加算税が課税されます。国税関係帳簿書類に不備や誤りが多いと推計課税が行われるケースもあります。
会社法による過料
電子帳簿保存法の対象となる書類を適切に保存しなかった場合、会社法の規定により罰金が課せられます。
このように電子帳簿保存法には罰則が設けられているため、電子取引を行う企業は対応が必要です。
2023年12月末まで宥恕措置が取られている
企業にとって、この電子帳簿保存法の改正は大きな変化です。そのため、なかなか対応が追いつかないことを見越し、宥恕措置として2023年12月末まで猶予期間が設けられています。
2022年1月から施行されていますが、電子取引を行っている事業者は、2023年12月末までに対応する必要があります。
インボイス制度・電子帳簿保存法のおさらい&おすすめツールはこちらから【HYPER VOiCE】インボイス制度・電子帳簿保存法ポータル
2023年12月末までに対応すべきこととは

では、2023年12月末までに企業はどのような対応が必要なのでしょうか。
対象となる書類の確認
電子保存義務化が適用される書類は、電子取引での取引情報が含まれるものです。
例えば、注文書や契約書、送り状や領収書、見積書、請求書など。まずは電子取引を行っているか、確認が必要です。
電子取引のデータ保存要件を満たすシステムの導入
電子取引を行った場合は、要件を満たすように保存しなければなりません。この保存要件を満たすには、真実性の確保と、可視性の確保が必要です。
真実性の確保
・記録の訂正や削除の事実が確認できる(帳簿のみ)
・通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴が確認できる(帳簿のみ)
・電子化した帳簿の記録と、その帳簿に関連する他の帳簿の記録事項同士との間において、相互にその関連性の確認ができる(帳簿のみ)
・システム概要書やシステム仕様書、など、システム関係書類を備え付ける(帳簿と書類が対象)
可視性の確保
・保存場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ、これらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書類に整然とした形式・明瞭な状態ですぐに出力できる(帳簿と書類が対象)
・取引年月日・勘定科目・取引金額、その他のその帳簿に応じた主要な記録項目により検索できる(帳簿と書類が対象)
・日付または金額の範囲指定で検索できる(帳簿と書類が対象)
・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる(帳簿のみ)
これらの要件を満たすシステムを導入する必要があります。
また、今回の電子帳簿保存法改正により、業務の社内フローが変わる場合があります。
インボイス制度・電子帳簿保存法のおさらい&おすすめツールはこちらから【HYPER VOiCE】インボイス制度・電子帳簿保存法ポータル
インボイス制度への対応も忘れずに
電子帳簿保存法が改正されましたが、それだけではありません。2023年の10月からは、インボイス制度が開始されます。このインボイス制度は、適格請求書等保存方式のこと。一定の要件を満たした適格請求書を用いて消費税の仕入税額控除を算出し、証拠資料として保存します。2023年10月までにインボイス制度への対応も必要となります。
インボイス制度については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
2023年の10月からインボイス制度が開始されます。このインボイス制度は、ネガティブな意見も多いことから、どのような制度なのか気になる方も多いのではないでしょうか。 そこで、...
続きを読む
まとめ
今回は、電子帳簿保存法について解説しました。
電子帳簿保存法は、改正され2022年から施行されています。とはいえ、変更への対応が大変なこともあり宥恕措置が取られ、2023年12月末まで猶予期間が設けられています。そのため、企業は2023年12月末までには対応が必要です。社内整備ができているか確認しておきましょう。
インボイス制度・電子帳簿保存法のおさらい&おすすめツールはこちらから【HYPER VOiCE】インボイス制度・電子帳簿保存法ポータル

「クラウドインフォボックス」では、働き方改革や経営に役立つクラウドサービスの情報を掲載しています。
姉妹サイトである「HYPERVOICE(ハイパーボイス)」では、企業様の情報システム代行サービス「Business Core NEXT(ビジネスコアネクスト)」や、クラウドサービス導入支援サービス「クラウドコンシェルジュ」を運営しております。
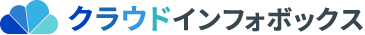
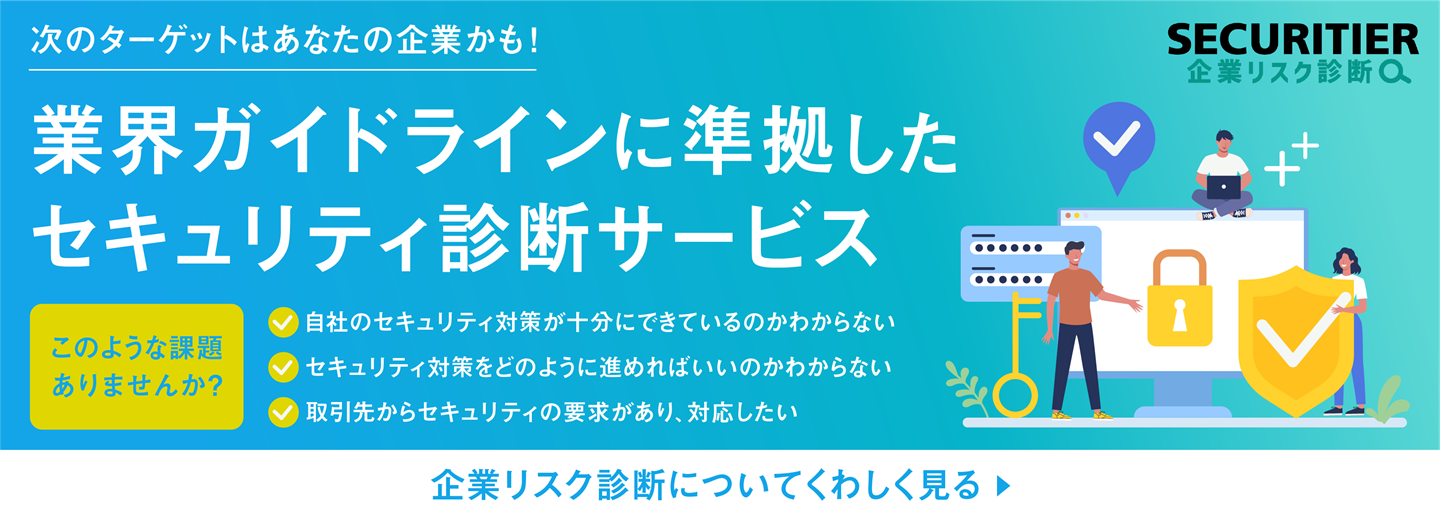


 インボイス制度は企業に影響する?インボイス制度が企業に与える影響
インボイス制度は企業に影響する?インボイス制度が企業に与える影響  2023年10月から開始のインボイス制度とは?制度導入前に企業がやるべきこと
2023年10月から開始のインボイス制度とは?制度導入前に企業がやるべきこと  在宅勤務手当は必要?在宅勤務手当について
在宅勤務手当は必要?在宅勤務手当について  フリーアドレスのメリットは?フリーアドレスが向いている企業
フリーアドレスのメリットは?フリーアドレスが向いている企業 